その日、いつもならまだ残業しているはずの時間帯。
会社から一時間ほど電車に揺られて我が家のある町へと帰ってきた私は、いち早く改札を抜けると、目的地を目指して足早に駅前の広場へと向かった。
「今日はすごい人だなぁ」
平日の夕方にも関わらず、広場はいつも以上にごった返している。
都心から一時間のベッドタウンだが、この近辺では栄えているエリアということもあり、駅前には深夜まで営業しているスーパーや飲食店も多い。
特に、ここ数年で駅ナカ広告やお店の看板がどんどんデジタルへと変わったことで、この駅前でも大小さまざまなディスプレイで商品の写真や映像を流していて、こうして日が暮れたとはいえほとんど暗さは感じなかった。
それにしても、今日は行きかう人々も町自体も、いつもよりもどこか浮かれているように見える。
その理由は、おそらく私が急いで帰ってきたのと同じだと思うのだが、それは――。
などと考え事をしていたせいか、
「うわぁっ?!」
角を曲がったところに現れた黒い集団に、思わず大声を上げてしまった。
そんな私の声に、当の黒い集団──トンガリ帽子を被った魔女らしき仮装をした、中学生くらいの女の子3人組──も驚いたのか、しばし道の真ん中で互いに固まってしまう。
が、やがて3人で顔を見合わせると、クスクスと笑いながら私の横を通り抜け駅の方へと駆けていった。
「あぁ、ビックリした。あの子たちも、ハロウィンかな?」
駅前の広場に向かうのであろう楽しそうな少女たちの後ろ姿を見送りながら、私は先ほど通り抜けてきた広場の様子を思い返していた。
私が子供の頃は存在すら知らなかったハロウィンだが、いつの間にやらすっかり市民権を得ていたようだ。
こんな郊外の町でも、今年から町内会主催でハロウィンの仮装行列をやることにしたらしい。
行列への参加は老若男女問わずとのことだが、高校生までの子供にはおやつがもらえるとあってか、駅前にはすでにいくつかのグループが出来上がっているようだった。
私の息子も先週から妻に頼んで仮装の準備をしたりと行列に参加するのを楽しみにしていたようだったが、昨日の夜に熱を出してしまったせいで、今朝妻から外出禁止令が出されていた。
おかげで、今朝はぐずる息子をなだめるのに一苦労だった・・・。
それもあって、家でぶんむくれているであろう息子のために、せめてハロウィンのお菓子を買って帰ろうと、上司の残業攻撃をひらりと交わして定時で帰ってきたのだった。
「おっと、いけない」
ふと腕時計を見ると、もう19時半を過ぎていた。お菓子屋さんは確か20時までのはず。
私は息子の喜ぶ顔を思い浮かべつつ、店へと急ぐ。
その道すがらにも、仮装姿の子供たちと何度もすれ違った。小学生くらいの子供たちのゾンビの集団もいれば、親に手を引かれて嬉しそうに歩いている小さなオオカミ男もいる。
それにしても、いくらイベントがあるとは言え、こんなにたくさんいるとは。
「こりゃあ、うちの息子は参加できなくて、相当拗ねてるだろうなぁ」
苦笑いでそう呟いたところで、通りの向こうに目当ての店が見えた。遠目でも分かるくらいに、ハロウィン仕様で黒とオレンジに彩られている。私は流れる車越しにショウウィンドウを眺めながら、信号が変わるのを待って横断歩道を渡った。
自動ドアが開くのを待つのももどかしく、足早に店へと入った途端──、
『トリック・オア・トリート!!』
「うおぉっ?!」
私は、本日2度目の悲鳴を上げていた。
慌てて周囲を見渡すと、ケーキやクッキーの並んだショウケースの向こうに、これまでも私と同じような反応をする人間が何人もいたのか、申し訳なさそうに頭を下げる女性店員の姿が見える。
そして、先ほどの声が聞こえてきたあたりには縦長の大きなディスプレイがあり、『ハッピー・ハロウィン!』と表示された画面には、まるで写真アプリの画面のようにハロウィンの仮装姿の小さな子供たちがたくさん並んで映し出されていた。
これはいったいなんだろうかとしばらく画面を眺めていると、いくつかの写真がパタパタとひっくり返って、違う子供の写真に入れ替わる。
どうやら、いろんな子供の写真が順番に表示されているようだった。
その子供たちの中にどこかで見たような子がいた気がして、私は目を凝らす。
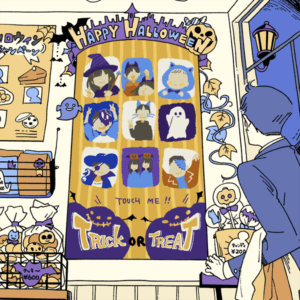 そこに映っている小さな魔女は、息子と同じ幼稚園に通う、お向かいの娘さんだった。それに気づいてから改めて子供たちをよく見てみると、そこかしこに近所の子供たちがいることに気付く。
そこに映っている小さな魔女は、息子と同じ幼稚園に通う、お向かいの娘さんだった。それに気づいてから改めて子供たちをよく見てみると、そこかしこに近所の子供たちがいることに気付く。
そして、真ん中の写真がパタリとひっくり返ったところで、思わず「あっ」と声が漏れた。
「これ、うちの息子じゃないか」
「あら~。この坊や、あなたの息子さんなの?」
私の声に気付いたのか、ちょうど商品補充に通りかかったらしい店主の女性が、ひょいっとディスプレイを覗き込んでくる。
「これ、おもしろいでしょう? 『デジタルサイネージ』っていうらしいんだけど」
「へぇ~、『デジタルサイネージ』。なんか、オシャレですね」
私の言葉に女性はニコニコと笑いながら、チラリとショウケースの方を見た。
「いえね、わたしはこういうのはとんと疎いんだけど。娘が、どうしてもって言うものだから」
つられてそちらを見ると、先ほどの女性店員が今度は笑顔で会釈をしてくれる。彼女が娘さんかと思いながら、私も会釈を返した。
「これねぇ。この子たちみぃんな、うちのお客さんとこのお子さんたちなのよ。お母さんに、携帯で写真とムービーを撮ってもらって、なんとかっていうのにアップロードしてもらうと、これに映るんだって」
「へー! なんかスゴイですね!」
「でしょう? 私らの時代は、こういう立て看板なんて業者さんに作ってもらうか、紙に描いてボードに貼りだしたりなんてしたもんだけど。最近は、テレビと携帯でこんなことも出来るんだって、なんか感動しちゃってねぇ」
店主の言葉を聞きながら、改めてディスプレイ――『デジタルサイネージ』をじっくりと眺める。
うん。確かに、これは感動するかもしれない。
と、視線を一番下におろしたところで、 【トリック】と【トリート】という2つのボタンがあることに気付く。
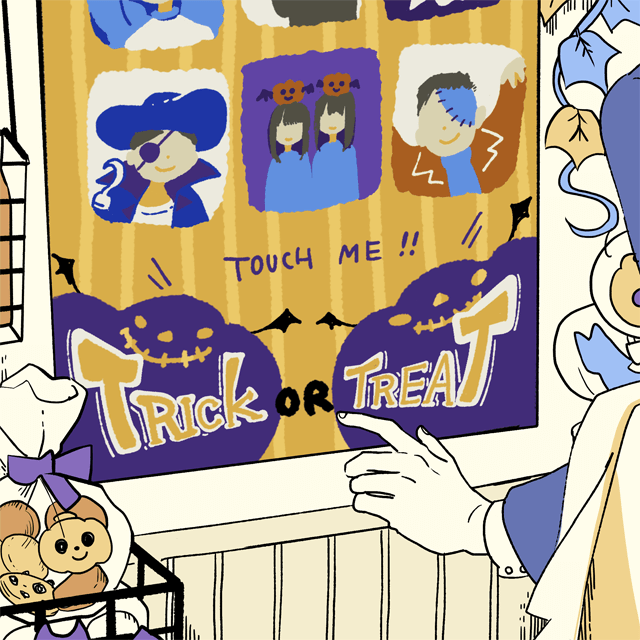
「あれ? このボタンはなんですか?」
言いながら私は、何気なく左側のボタン――【トリック】に手を伸ばした。
「あっ、それは」と女性店員が何か言いかけたところで、
『ばぁっ!!』
「わぁっ!?」
私は、さすがに慣れてきたのか先ほどよりは小さめの、本日3度目の悲鳴を上げた。
「それ、子供たちからの『トリック・オア・トリート』へのお返事を、ボタンで選んでもらう仕組みになってるんです」
笑いをかみ殺した様子で、店員がショウケースの向こうから良く通る声で説明をしてくれる。
「【トリック】を選ぶと、そうやって子供たちが驚かすムービーが流れるんですよ」
なるほど、確かに画面の中では白い布を被ったオバケが、精いっぱい怖がらせようとユラユラと揺れていた。
「それじゃあ、この【トリート】を選ぶと……?」
私が【トリート】のボタンに触れると、オバケが消えてまた別の画面へと切り替わる。
するとそこには、先ほどの子供たちの写真と同じように、いろんなハロウィンデザインのお菓子がたくさん並んで表示されていた。
「そんな風に、【トリート】を選ぶと子供たちにお菓子をプレゼントできる仕組みになってるんです!」
店員が、心なしか前のめりになって説明を続けてくれる。
「そのボタンを押してくれた皆さんが買ってくれたお菓子を、あとで小分けにして、私たちから皆さんにお届けするんですよ」
「なるほど。これはよく出来てる」
私は、妙に感心してしまった。
近所の子供たちに、しかもこんなにかわいい魔女やオバケにおねだりされたら、お菓子を買わないわけにはいかない。
しかも、それを町のみんなでワリカンしてるようなものなので、金額的にも大したことないとなればなおさらだ。
「いやぁ、これはズルい。
ズルいけど、確かに『ハッピー・ハロウィン!』ですね」
私は自然と頬が緩むのを感じながら、画面に表示されたお菓子の中からなんとなくお向かいの娘さんが好きそうな、かわいいオバケの形をしたチョコレートの詰め合わせを選んだ。
それから、ショウケースの中から、こちらもハロウィンデザインになっている、息子の好物であるビスケットを注文する。
「ありがとうございましたー! ハッピー・ハロウィン!」
そうして2つ分の商品の支払いを済ませると、店員の声に送られながら店を後にした。
「よーし。それじゃ、早く帰ってやるかぁ」
私は、今日これからの息子の笑顔と、そして数日後にもう一度見られるであろう笑顔を思い浮かべながら、妻と息子の待つ我が家へと家路を急ぐ。
なんだか、すれ違う子供たちみんなに、
『ハッピー・ハロウィン!』
と声をかけて回りたいような、そんな気分だった。
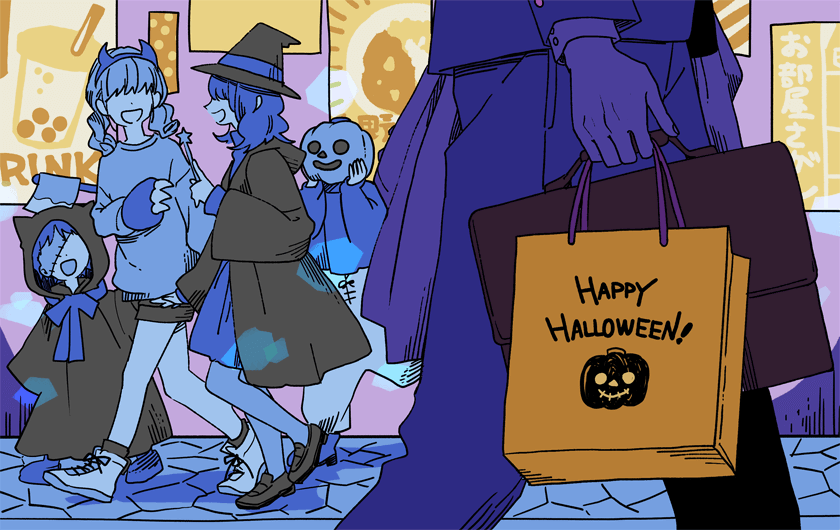
はじめまして。Yumenoと申します。
このたび、縁あってDDSさんで『かもしれないサイネージ』というテーマで物語を書かせていただくことになりました。
このシリーズは、「デジタルサイネージが普及すると、こんな出来事もある『かもしれない』」や、「デジタルサイネージによって、世の中が今よりももっと幸せに『なるかもしれない』」という着想から、実際にある『かもしれない』ほんの少し未来の世界を描いたものです。
今回取り上げた【デジタルサイネージ】は、例えばショッピングモールのフロアマップで採用されているような、タッチパネルタイプのものです。それがもっと手軽に、かつネットワークで繋がることで、コミュニティの活性化や地域密着型の新しいビジネスモデルが生まれるのではないかと、個人的にはちょっと期待していたりします。

